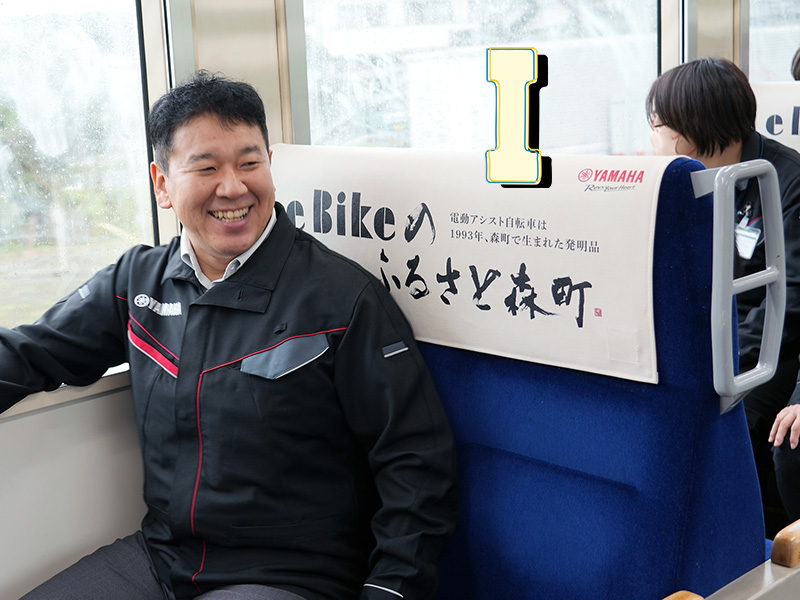ミニ四駆体験で地域の子どもたちにモノづくりの楽しさを伝えたい



ミニ四駆体験で地域の子どもたちに
モノづくりの楽しさを伝えたい

少年時代に熱中した趣味との再会
子どものころ、夢中になったものは何ですか? 電車、お絵描き、昆虫採集……みなさんにもいろんな思い出があることでしょう。 私は小学生のころ、ミニ四駆に夢中でした。
ミニ四駆は小さなモーターで走る自動車模型で、1980年代後半には全国的な大ブームになりました。デパートの屋上では週末ごとにレースイベントが開かれ、たくさんの子どもたちで賑わっていました。私は少しでも速く走らせようと、なけなしのお小遣いでパーツを買い替えたり、ドリルでボディを肉抜きして軽量化したりと、子どもなりに頭を使って改造していました。
当時は子どもだけでお店のコースを利用するのが難しかったので、自宅にコースを持っている子は近所のヒーロー。みんなの憧れの的でしたね(笑)。その子の家に行って走らせてもらったり、道路の排水溝が干上がったところをコースに見立てて遊んだりしていました。
そんなふうに夢中だったミニ四駆も、中学生になるころには熱が冷め、いつしか手に取ることもなくなっていきました。大学を卒業してヤマハ発動機に入社し、静岡に移り住んで結婚。再びミニ四駆と出会ったとき、私は父親になっていました。
ある日家族でショッピングモールを訪れるとミニ四駆のイベントが開催されていて、子どもたちが「やってみたい」と言い出します。それに付き合って一緒に組み立てたり走らせたりするうちに、私自身がすっかりハマってしまいました。人生で二度目のミニ四駆ブームの到来です。
常設コース撤去を機に、同好会を発足!
それからは子どもたちと一緒にミニ四駆のコースがあるお店で走らせたり、レースに参加したりと、かつてのようにミニ四駆で遊ぶようになりました。
大人になると「どうすれば速くなるか」がよくわかるうえに、昔と比べて改造にお金もかけられるので、子どものころとはまた違う楽しみがあるんですよね(笑)。社内でも同じようにミニ四駆を楽しむ仲間がいることがわかり、情報交換をするようになりました。
しかし時代の流れなのか、次第にお店から常設コースが姿を消していき、ついには近所のコースがすべて撤去されてしまいました。このままでは私と子どもたちも遊べませんし、そこで遊んでいた他の子どもたちの居場所もなくなってしまいます。
「遊び場がないなら、自分たちで作るしかない」
そう考えて、社内の仲間に声をかけ、2018年に同好会を発足しました。仲間と一緒に少し離れたお店へ遠征したり、磐田市内のホテルの一室を借りてコースを設営し、イベントを開いたこともありました。
そんな活動のなかで、私とメンバーは「もっと多くの子どもたちにミニ四駆の楽しさを知ってもらいたい」と思うようになりました。そんなとき、ヤマハジャンボリーの事務局の方とつながり、「2019年に出展してみませんか?」と声をかけてもらったのです。
ヤマハジャンボリーは、ヤマハ発動機と労働組合が主催する地域イベントで、モーターサイクルの始動体験やトライアルショー、抽選会やスタンプラリーなどが行われています。そこでコミュニケーションプラザの会議室をお借りして、ミニ四駆の工作体験会を企画しました。

初めての体験会は想定外の大盛況、そして大反省!?
初めてのイベントということもあり、「せいぜい親子10組くらいかな」と予想してキットを準備していました。ところが、いざ当日を迎えると次々と子どもたちが来場します。
チラシを見て来た親子連れだけでなく、「自分もかつてハマっていた」と昔を懐かしんで子どもを連れてきた親御さんも多く、想定をはるかに超える反響でした。
なんとその日は78人(!)の子どもたちが参加。私たちスタッフは何度も中抜けして、補充用のミニ四駆キットを買いに走ることになりました。キットの数だけでなく会場のスペースも足りず、せっかく来てくれた方をお待たせしてしまって見積もりの甘さに反省しきり。心苦しさと大きな喜びを同時に感じた初回の体験会でした。
それでも参加した子どもたちは本当に楽しそうにミニ四駆を組み立てて、出来上がったマシンを親に自慢して大喜び。想定外の来場者数でイベントが終わるころにはスタッフはぐったりしていましたが、子どもたちの笑顔がうれしくて「もっとこの活動を広げていきたいな」と思うようになっていました。
このイベントをきっかけに、それ以降も地域の子どもたちに向けて定期的に体験会を開催するようになり、同好会は会社の正式な認定クラブへと昇格。現在は12名のメンバーで、年に5〜6回の体験会開催と、メンバーでのレース活動という二本柱で活動を続けています。
レースが子どもたちに教えてくれること
体験会はコミュニケーションプラザを中心に、最近ではコジマ×ビックカメラ浜松店と協賛することもありました。常連のリピーターさんを中心に、ときには長野県や岐阜県など遠方から来てくれる方もいます。
活動で一番のやりがいは、やっぱり子どもたちがたくさん集まってくれること。
「ぐっさーん!」と私に駆け寄ってきて、キラキラした目で自慢のマシンを見せてくれる姿を見ると、本当にうれしいです。仕事の疲れも一気に吹き飛びます。
ところがレースが始まると、子どもたちの表情は一転。勝利を目指す真剣な眼差しになり、勝てば大喜び、負ければ悔し泣きする子もいます。そんな一生懸命な姿に、こちらが胸を打たれることも少なくありません。
ときには「ぐっさん、勝負しよう!」と挑まれることもあります。
子どもたちと勝負するときは、自分が所有するマシンではなくレンタル車両を微調整して走らせます。でも油断すると負けることもあるような、絶妙なバランスで競り合うレースに仕立てるのが、私の腕の見せどころです。
レースは勝っても負けても、子どもたちにさまざまな感情をもたらし、成長させてくれる場です。 本気で挑むからこそ、成功体験だけでなく、悔しい思いもする。その中で折れずに工夫して次に進む――。そんな姿勢を、子どもたちに大切にしてもらいたいと思っています。
子どもの可能性を広げる「知育玩具」
子どものころはただ夢中で遊んでいましたが、大人になった今、改めて感じるのは「ミニ四駆はとても優れた知育玩具だ」ということです。 「組み立てる」ことで手先を使い、モノづくりの楽しさを知る。「走らせる」ことで競争心が養われるので、勝つための工夫を考え、思考力を養う。私はいまホイールの設計を担当していますが、ミニ四駆でモノづくりに触れた経験が、現在の仕事につながっていると感じています。
また、ミニ四駆は意外にも社会性やコミュニケーション能力を育む遊びです。イベントでは初対面の子ども同士が自然に一緒に遊ぶようになり、年上の子が年下の子に作り方を教える姿もよく見られます。そうした「教え、教わる」サイクルが生まれていることに、私自身も活動を通じて気づきました。
この素晴らしさを一人でも多くの子どもたちに伝えるため、これからも定期的にイベントを続けていきたいと思います。それにはまず活動を知ってもらうことが大切なので、SNSやYouTubeでの情報発信にも力を入れています。大人の参加も大歓迎です。ぜひご家族で遊びに来てください。
私の夢は、イベントに来てくれた子どもたちが大きくなって「ぐっさん、ヤマハ発動機に入社したよ!」と声をかけてくれること。そして今度はクラブメンバーとして、本気のレースで再び競い合える日を心から楽しみにしています。