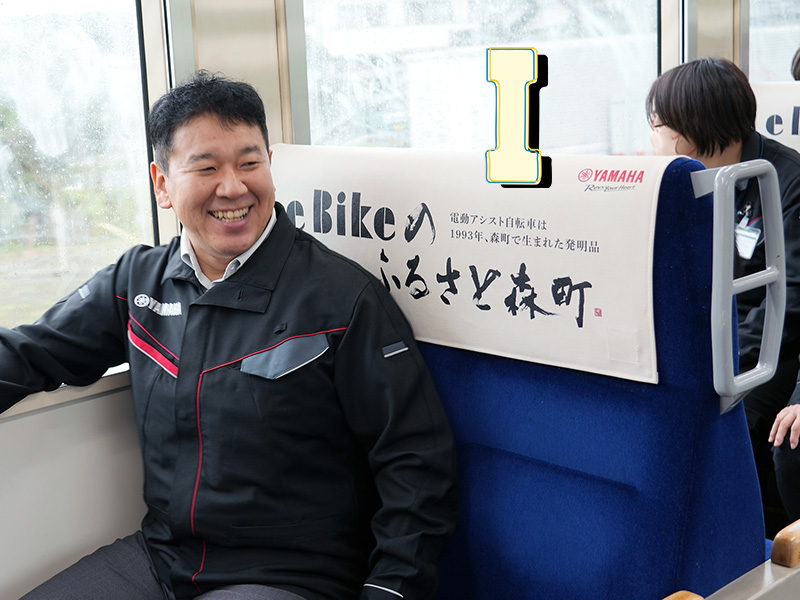モビリティの活用で三ヶ日町を盛り上げたい 週末ボランティアから共創プロジェクトへの道のり



モビリティの活用で三ヶ日町を盛り上げたい
週末ボランティアから
共創プロジェクトへの道のり

浜松市長からもエール! 三ヶ日町の地域共創プロジェクト
2025年3月13日、株式会社BLUE LAKE Projectとヤマハ発動機は共同で地域共創への取り組みを宣言しました。これは浜松市三ヶ日町を中心に、2社と地域が協働し、ヤマハ発動機の製品や技術を活用した新しいビジネスモデルやサービスを創出しながら、豊かで持続可能な社会を作るためのものです。浜松市もこの取り組みを支援することになり、当日は中野市長から力強い励ましのメッセージをいただきました。また共同宣言の調印式には地域の方々が集まり、手作りのヤマハ発動機の旗を振って応援してくれました。その光景を目の当たりにして、胸の奥からぐっと力が湧いてくるのを感じました。
株式会社BLUE LAKE Project は三ヶ日町の地域資源を活かしてさまざまな取り組みを行っている企業です。地域の魅力を体験するイベントの開催や、摘果みかんを活用したオリジナル商品の開発・販売など、地域の未来を見据えた活動を展開しています。現在私がリーダーを務める社会共創プロジェクトでは、彼らとともに「三ヶ日浜名湖クリエイティブフィールド」の実現に向けて準備を進めています。今回はこのプロジェクトの概要を紹介するとともに、いまや私のライフワークになりつつある地域共創についてお伝えしたいと思います。
やりがいと居場所をくれたボランティア活動
私がクリエイティブ本部に異動してきたのは2022年のこと。この部門の活動として、「Town eMotion」など新たな価値を創造する取り組みを進めていました。人間らしい幸せや豊かな社会づくりに対して、ヤマハ発動機はモビリティでどのように貢献し、価値を提供できるのか。そんなことを模索する毎日です。
その仕事のなかで出会ったのが、地域共創(企業・行政・大学等が地域との共創活動を通じて、社会課題の解決や持続可能な社会づくりを目指す取り組み)でした。しかしヤマハ発動機に入社して約30年、私の生活の中心は常に会社にあり、いままで地域社会と関わったこともなければ、地域目線で物事を考えた経験もありません。地域共創を自分なりに学んで実践するために、まず自分が地域社会に出て人と交流してみよう。そう考えて、週末はボランティアとして地域活動に参加することにしたのです。
ひとことで地域活動と言っても、ゴミ拾いからイベント運営までその内容はじつに多種多様です。なかでも恐竜の着ぐるみを着て競走するティラノサウルスレースというイベントは、大人も子どもも盛り上がってくれて印象に残っています。とは言え当初は周りにほとんど知り合いもなく、自分が何をすればいいのかわからず何となくその場にいるだけ、ということもありました。しかし半年ほど続けているうちに地域の人の顔と名前が一致してきて、活動のなかで自分が何をやるべきか見えてくるようになったのです。次第に地域の方々も「吹田さん」と名前で呼んでくれるようになり、少しずつ地域のなかに「自分の居場所がある」と感じられるようになりました。仕事に活かすための経験、そんな気持ちで参加し始めた週末のボランティア活動でしたが、いつの間にかそれは自分自身の楽しみに、そして生きがいへと変わっていきました。

あらゆるヤマハ発動機製品で遊べる町
私は浜松市の市街地に住んでいるため、三ヶ日町でボランティアをすることになったきっかけは地域活動で知り合った人からの紹介でした。でも、じつは以前から三ヶ日町は個人的によく訪れている場所でもありました。ちょっと気晴らしにオートバイを走らせれば素晴らしい景色に出会えるし、美味しい食べ物もたくさんある。住民の方も開放的で気軽に挨拶してくれたりと、訪れるたびに親しみや懐かしさを感じていました。
その一方で、この町は現代日本の縮図のような問題を抱えています。主要産業である農業は少子高齢化で後継者不足が深刻化し、耕作放棄地が増えています。また地域の雇用機会の減少で、若者の地元離れも進んでいます。このような地域課題の解決に長年取り組んできた人たちが一緒になって2019年に立ち上げたのが株式会社BLUE LAKE Projectです。私はプライベートのボランティア活動で彼らと知り合い、それ以来さまざまな地域活動で関わりながらお互いの思いや展望を語ってきました。それがいつしかヤマハ発動機として三ヶ日町の地域共創に一緒に取り組めないか、という話に発展していったのです。
その背景には、三ヶ日町ならではの地域資源の存在があります。浜名湖や周辺の森林など豊かな自然環境は、ヤマハ発動機製品を使って遊ぶフィールドとして大きなポテンシャルを秘めているのです。景観の美しい湖畔の道はオートバイや自転車で走るのに最適ですし、浜名湖ではマリンスポーツのほか、観光クルージングを楽しむこともできます。グリーンスローモビリティ(※)は観光スポットやレストランを巡るツアーに活用したり、地域住民の移動手段としても役立ちます。三ヶ日町で観光客や地域住民にヤマハ発動機製品を活用してもらうことが、地域活性化だけでなく新しいビジネスモデルの創出にもつながっていくのです。
(※)時速20km未満で公道を走る、4人乗り以上の電動パブリックモビリティ

信頼関係で乗り越えた「不安の壁」
現在私たちのプロジェクトチームでは、天竜浜名湖鉄道の三ヶ日駅周辺にベースキャンプとなる拠点づくりの準備を進めています。ここは株式会社BLUE LAKE Projectが運営する拠点で、観光客向けの電動アシスト自転車のレンタルや特産品の販売に加え、シェアオフィスとして地域のスモールビジネスを支える場とする予定です。そして何より地域の人のコミュニケーションスペースとして、気軽に訪れる場所にしたいと考えています。地域の仲間や観光客と交流したり、地元の美味しい食を楽しめるサードプレイス。暮らしのなかでそんな豊かな時間を持てる場所づくりを目指しています。
とは言え、ここまでプロジェクトがすべて順調に進んできたわけではありません。いきなりヤマハ発動機という大企業が関わってくることに対して、地域のなかには警戒心をもつ方もいらっしゃいました。
「急に何かが建設されて、自分たちの暮らしが変わってしまうんじゃないか」
「儲からなければすぐに撤退し、建物だけが残って荒廃しかねない」
という声も聞かれました。そういった不安に対しては、株式会社BLUE LAKE Projectとともに地域の方と交流し、時間をかけて対話を重ね、お互いの理解を深めながら信頼を築いていきました。
地域の人と、ヤマハ発動機の仲間と、これからもずっと
現在私たちのプロジェクトは三ヶ日町で活動していますが、社内では磐田市や森町で同様の取り組みを展開しているチームもあります。これらの活動を全部つなげて、遠州全域に広げていくことが今後の私の目標です。それが実現すれば、ヤマハ発動機の地域共創の取り組みは日本におけるモデルケースになるのではないでしょうか。日本各地で同じような課題を抱える地域と企業がともに活動し、持続可能な社会をつくる取り組みが広がっていくことを願っています。
また個人的な話になりますが、ここ数年のボランティア活動で自分自身にも大きな変化がありました。私は福岡県北九州市の出身で、ヤマハ発動機に入社するために浜松に来たので、浜松は「働くための場所」という感覚がずっと残っていたのです。それがある時から、帰省して浜松に戻ると「帰ってきた」と感じられるようになりました。そのとき、自分もやっと遠州の人間になれたんだな、と実感しました。
ほかにも株式会社BLUE LAKE Projectのメンバーたちが、いつの間にか私の名刺を用意してくれていたのも嬉しい出来事でした。そこにある「取締まられ役MDK(三ヶ日大好き会社員)」という肩書には思わず笑ってしまいましたが、同時に地域の仲間として認められた誇らしさを感じさせてくれました。
いまでは地域活動の場は、すっかり私のサードプレイスになっています。会社と家庭以外に自分の居場所を持てたことで気持ちに余裕が生まれ、会社で働く時間も家庭で過ごす時間も以前より充実しています。会社に依存しすぎることもなく、力が抜けて自然体の自分でいられるようになったので、仕事においてもパフォーマンスを発揮できるようになりました。いまは地域共創が会社の仕事につながりましたが、この共創活動は地域のなかで自分が生涯働いていける場所づくりになっているような気がします。そして定年退職してからも、自分のライフワークとしてヤマハ発動機や地域の仲間と関わりあいながら、地域社会で豊かな暮らしを送っていけたらいいな、と思います。