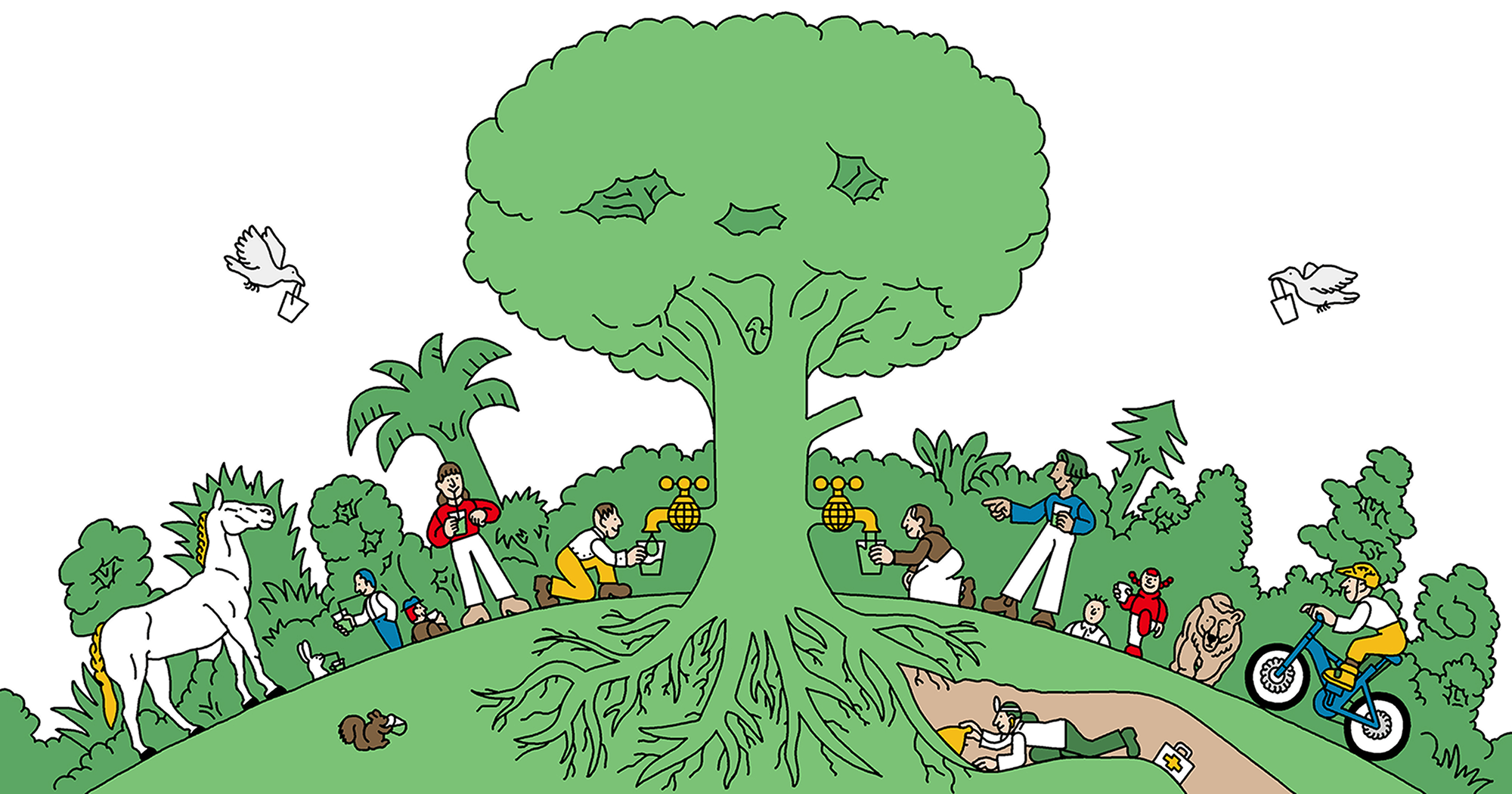ロジックを超えて揺さぶれ。イヨシコーラに宿る「ワクワク」という名の反逆精神
クラフトコーラ専門メーカー伊良コーラ(イヨシコーラ)を立ち上げたコーラ小林さんが語る、熱量を軸にしたブランドづくりの哲学とは?
クラフトコーラ専門メーカー伊良コーラ(イヨシコーラ)を立ち上げたコーラ小林さんが語る、熱量を軸にしたブランドづくりの哲学とは?
ヤマハ発動機の中に、少しユニークな取り組みをしている部署があります。名前は「共創推進グループ」。社外パートナーと手を組みながら、サステナブルのその先にある「リジェネラティブ(再生的)」な事業の創出を目指しています。
そんな部署に所属する和田朋智毅と鈴木啓文が挑んでいるのが、森林再生をテーマにしたドリンクの開発です。群馬・谷川岳の山道をマウンテンバイクで走っていたある日、「この瞬間に飲みたくなるような一杯を、自分たちの手でつくれないか?」と考えたのが、すべての始まりでした。

プロジェクトを進める中で見えてきたのは、地域に根深く残る林業の衰退という課題。そして、香り高い樹木・クロモジとの出会い。「森を元気にしながら、自然と人の距離を近づけるようなドリンクがほしい」という思いが彼らを突き動かす一方で、二人は飲料開発の素人。試作、社内プレゼン、そして伝わらない想い。アイデアだけでは超えられない壁がいくつも立ちはだかりました。
そこで今回二人は、伊良コーラ(以下、イヨシコーラ)代表・コーラ小林さんの元を訪ねました。ゼロからブランドを立ち上げ、育ててきた歩みの中に、自分たちが前へ進むためのヒントがあるのではないかと考えたのです。
どうすれば想いは人に伝わり、広がっていくのか。「誰もやったことがないこと」を形にしていく、その手がかりを探ります。

 そのアイデア、本当にワクワクしてる?
そのアイデア、本当にワクワクしてる?
事前に頂いた資料も拝見しました。きれいにまとまってる。でも、なんか引っかかったんですよね……。つかぬことを聞きますが、本当にクロモジ、好きですか?
例えば、「クロモジってめっちゃすごい植物なんです。まずはこの香りを嗅いでみてください!」って言いながら、突然ポケットからクロモジを出してくるみたいな勢いがあったら、もうそれだけで伝わるというか。一方で、クロモジって香りもすごいいいし、林業の再生につながるし……って頭で考えちゃうと、なんかうまく伝わらないんですよね。まずは相手が「え、何それ?」って思うくらいの熱量が必要だと思うんです。
そうですね。当時は意識していたわけではないんですが、今ふりかえって言語化してみると、趣味で作り始めたコーラを「誰かに飲んでもらいたい」と思った瞬間から、情熱の火がついていたように思います。これはすごいことになる、革命が起きるぞ!って。

最初のキッチンカー「カワセミ号」をつくったときも、すごくワクワクしていて。車代やシンクの購入費など、諸々含めて300万円ぐらいかかったのですが、貯金を全額突っ込みましたね。デザイナー探しから、ブランドのコンセプトづくり、パッケージの制作まで、すべてゼロから。しかもそれを、2か月で形にするというスピード感でした。
そのとき実感したのが、アウトプットの質はワクワクの度合いに比例するということ。それ以来、不安があってもワクワクできるならまず動いてみよう、ということが自分の信条になりました。
 文脈を拾い、かたちにする
文脈を拾い、かたちにする
実は意識的に作っているつもりはなくて、そこにあった文脈を拾っていただけ、という感覚なんですよね。祖父が和漢方職人だったことも、あとからふと思い出して「あ、これはつながっていたんだな」って。でも、そういう出来事や言葉を、一つひとつ丁寧に拾うことは意識しています。
そうやって、点と点がつながっていく中で、「形にしたい」という衝動が生まれてくるんです。神宮前に直営店をつくった時も、まさにそんな流れでした。
イヨシコーラができてから、「この商品をどうやって広げていくか?」をずっと模索してきたんです。卸にしても、缶で出すかシロップボトルにするのか、どの商品に注力するのかっていう選択肢があるし。広げるということだけで言えば、フランチャイズ化やプロデュース、監修という手法もある。そういう数ある手札の中から「直営店」を選んだのは、やっぱり目の前で直接お客さんに手渡すのが、一番熱量が伝わると思ったからです。

渋谷の直営店には、全世界からお客さんが来てくれて、カウンター越しに「Wow!」って驚いてくれるんです。メルボルンでポップアップをやった時も、びっくりするくらい人が集まって、イヨシコーラをきっかけに会話が生まれたり、笑顔になってくれたりして。
そういうリアクションが直で帰って来る場って、やっぱり特別なんですよね。僕らにとってコーラを届けるって、単に物を売ることじゃなくて、記憶とか感動を渡すことなんです。だからこそ直営店でイヨシコーラを届けるのが最強だと考えました。
 剥がした床に、思想が宿る
剥がした床に、思想が宿る
同じ現場で一緒に手を動かすことと、初期段階から関わってもらうことを大事にしてますね。浅草の店舗を最初に見たときは、ほんとにこれが店になるのか?っていう状態で。でも、でき上がった後に「よろしくね」って引き継ぐよりも、そういうゼロからの状態を一緒に経験することが、楽しいし、共有すべきだと思っていて。
だから今も浅草のお店をみんなでDIYしてるんです。床のタイルを剥がすと、当時のコンクリートが出てくるんですけど、糊の跡というか、紙のような素材が残ってて。それをヘラで1枚ずつ剥がしているんです。
コンクリートむき出しといっても、仕上げ方で表情が全然違うんです。例えば、上からコンクリートを打ち直せばツルっとした仕上がりになるし、ディスクグラインダーで一気に削れば「削りました」っていう機械的な跡が残ってしまう。でも、ヘラで少しずつ剥がしてくと、味わい深い“昔のままの表情”が出てくるんですよね。
効率やコストを優先すれば、こんなやり方はまず選ばないと思いますが、こういう熱意って、お客さんにちゃんと伝わると信じてるんです。
店舗に限らず、商品も、根っこは全部同じだと思ってます。だから「効率」で考えるじゃなくて、よりいい空間へ、よりいい味へ、感覚的に納得できる方に進む。結果的にそれが、お客さんにもちゃんと伝わるんですよね。言葉じゃなくても、空間や手触りを通して伝えられることって、たくさんあると思うので。
 理屈で通らない壁は、熱量で突破する
理屈で通らない壁は、熱量で突破する
それはありますよ。世の中にないものを作るっていう意味での苦労は絶えませんでしたね。例えば、コーヒー屋さんなら誰もがすぐにイメージできますが、「コーラ屋」と言われてもピンとこないじゃないですか。つまり、世の中にまだ定着していない仕事は、事業の内容や魅力を理解してもらうのが難しいんです。創業当初は商談で名刺の交換すらしてもらえなかったこともありますし、そもそも商談の場に呼んでもらえない、なんてこともありました。
浅草でお店を出すことも、最初は不安でした。浅草といっても人通りが多いエリアではないし、家賃相場もかなり上がっていて。そんな時に、同い年の友人が名古屋でビル一棟を丸ごと飲食店にしたという話を聞いたんです。しかも、その場所も人通りが少なく、周囲からは大反対されたそうで。それでも彼は、自分の感覚を信じて勝負に出た。蓋を開けてみたら、オープン初日から大行列だったそうです。自分を信じ抜くことの大切さを、彼の姿から教わりました。
だからこそ、僕は「熱量」を大事にしてるんです。結局、壁を突破するのって、そういう力でしかないと思っていて。それには、相手の心を揺さぶるほどの想いや、純粋なワクワクをいかに研ぎ澄ませていくかが勝負なんですよね。

もちろん、ロジカルな思考や合理的な判断も大事だとは思うんですよ。ただ、生半可なものじゃ通用しないというか。その土俵で戦う相手って、大企業の中にいる専門家だったり、大学の研究機関だったり、ガチでその分野を掘り下げてきた人たちだから。そこに中途半端な理屈で立ち向かったって、勝てるわけがない。だからこそ、僕らには僕らの土俵がある。熱量でしか開けない扉が、世の中にはあると思っています。
大きくは変わらないですね。ここでも、やっぱり熱量の向け方だと思います。もちろん、1年目からできていたわけじゃない。うまくハマるまでに3年くらいかかりました。プロジェクトに自分の熱量を注げたらいいけど、いつもそうであるとは限らない。例えば、お客さんをいかに喜ばせるかとか、仕事仲間との関係をよりよくするっていうような、熱量の対象を一つに絞らずに、寄ったり引いたりして見てみたらすごく楽しくなりましたね。
 凝り固まった価値観を破壊したい
凝り固まった価値観を破壊したい
僕は「今、お前が見ている世界は、一方的な見方なんじゃないの?」っていう、新しい視点や価値観を突きつけてくる映画や芸術作品が好きなんです。見慣れた景色がガラッと変わる瞬間があって、それにハッとさせられる。そういう意味で、僕も常に人をハッとさせたいと思います。
最近改めて気づいたんですが、僕の原動力って単なる「コーラ好き」だけじゃなくて、突き詰めていけば「世の中を変えたい」とか「革命を起こしたい」っていう衝動でもあるんです。
そうですね。これは、僕が日本生まれっていうのが大きいと思ってて。今のグローバルスタンダードってなんだかんだで西洋的な価値観が中心にありますよね。イヨシコーラを始めて、自分の中にそういった固定観念への怒りや疑問があったことを自覚するようになったんです。だからこそ、漢方をはじめとした東洋の思想を通じて、世界に揺さぶりをかけたい。クラフトコーラは、その“揺さぶり”を形にするための手段という感覚かもしれません。
常識を覆すようなアイデアで社会にインパクトを与え続けること。僕の中には「破壊者=ブレイカー」でありたいという思いが強くあるんです。凝り固まった価値観の世界に「感動」で風穴を開ける。それが、僕がこの先も目指していく生き方なんだと思います。

コーラ小林 1989年・東京生まれ。和漢方職人「伊東良太郎」を祖父に持つ。 北海道大学農学部卒業後、一般企業に勤務しながら、大好きなコーラ作りの探求を進め、2018年7月にクラフトコーラ専門メーカー・専門店「イヨシコーラ」を立ち上げる。
執筆:山本梓/撮影:金本凜太朗/編集:日向コイケ(Huuuu)