「MOTOROiD」と「LOVOT」から見る、愛着研究

Outline
「人機官能」という開発思想を掲げ、“人と機械の一体感”を追求するヤマハ発動機。そんな同社が昨年から取り組んでいるのが「愛着研究」です。
人がモノに抱く「愛着」とは何なのか。その曖昧な言葉をヒモ解く鍵となるのは、「MOTOROiD」と「LOVOT」というふたつのモノ。研究に携わる3名にお話を伺いました。
-

末神 翔
技術・研究本部 技術戦略部
人間研究ストラテジーリード2011年、上智大学大学院 総合人間科学研究科心理学専攻 博士後期課程修了。専門は認知心理学。博士(心理学)。オスロ大学心理学部(日本学術振興会海外特別研究員)や長崎大学(特任助教)を経て、2014年にヤマハ発動機に入社。人間研究ストラテジーリードとしてヤマハ発動機の人間研究の戦略立案から研究遂行までを担う。
-

林 輝宙
クリエイティブ本部
ブランドマーケティング部
リサーチャー2023年、千葉大学大学院 融合理工学府創成工学科デザインコース修了。同年ヤマハ発動機に入社。文化人類学や進化生物学など幅広い人文社会科学の知見を取り入れたデザインを志向。人間研究チームの一員として研究の仮説立案から遂行、プロトタイピングまでを担う。
根底にあるのは、「人と機械の一体感」
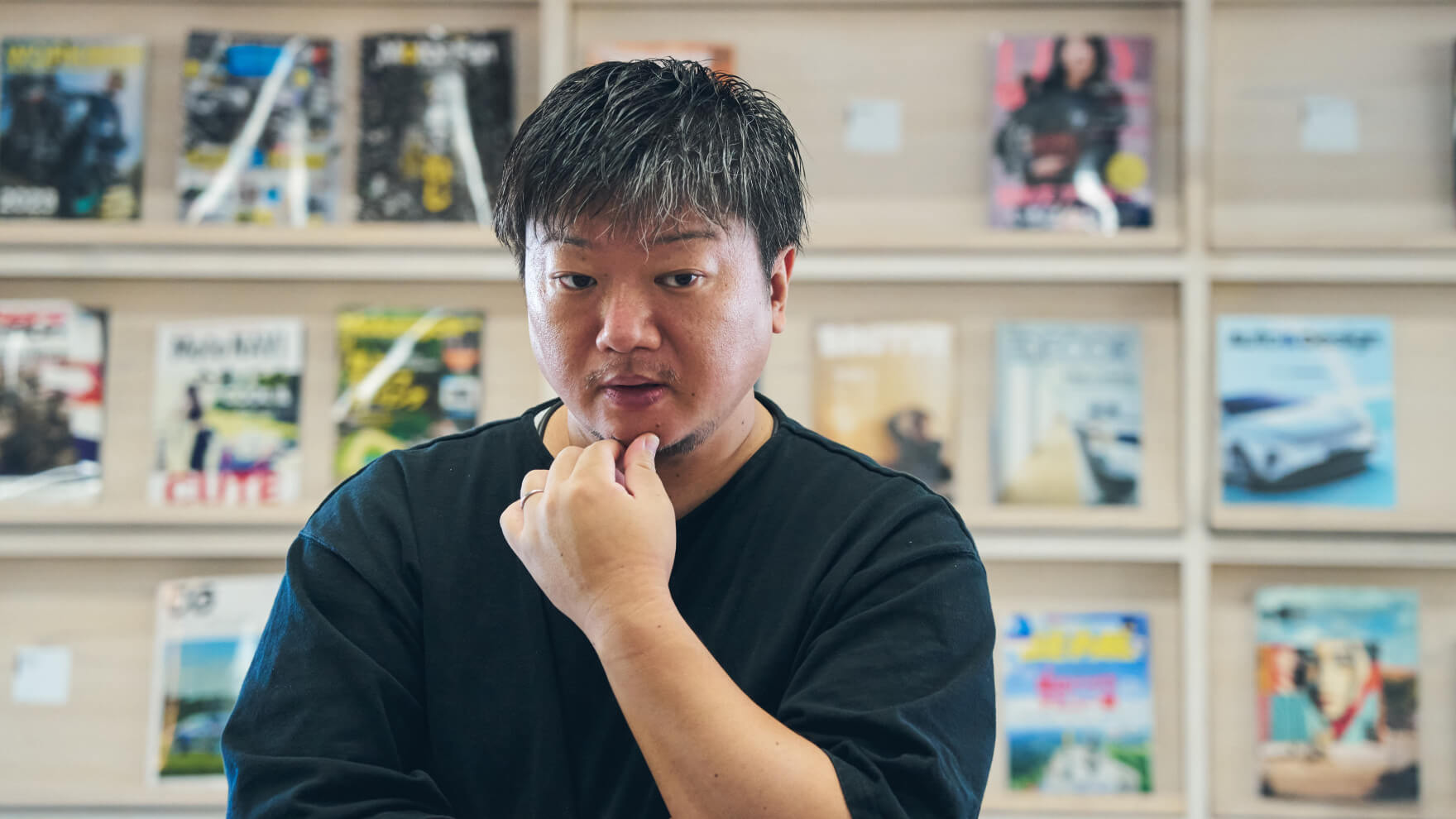
—— まずは、ヤマハ発動機の開発思想である「人機官能」について教えてください。
末神:人間が乗り物を意のままに操る悦びや興奮、快感を定量化し、製品に織り込んでいくという考えを指した言葉です。もともと社内では1990年代からあった言葉ですが、本格的に開発の軸となる思想として扱うようになったのは2015年ごろからですね。その際、当時の技術本部で言葉の意味を整理しようということになり、私が担当しました。社員1万人への質問紙調査や専門家へのインタビューなど、1年ほどかけていろいろな視点から考察した結果見えてきたのは、「人と機械の一体感」が根底にあるということ。この言葉こそ人機官能の核となる部分です。
—— 「人と機械の一体感」とは、具体的にどんなことでしょうか?
末神:いちばん大きいのは、自分のカラダの一部のように乗りこなせる、という身体的な一体感ですね。これは2015年以前もさまざまな場面でヤマハ発動機が追求してきたことです。例えばモーターサイクルの要であるハンドリングを、人間の感性に馴染む自然な応答性を突き詰めた「ヤマハのハンドリング」として打ち出しています。こうした身体的な側面での一体感というのは、イメージしてもらいやすいかと思います。
そしてもうひとつ。人機官能という言葉を研究する中で新しく見えてきたのは、一緒に時を過ごすパートナーとしての精神的な一体感です。いわゆる愛着のようなものですね。身体的な一体感は他社を含めて色々な形で研究されていますが、精神的な一体感を技術的に実現していこうという取り組みは、当時、社内を含めてなかなかない取り組みでした。暗黙的に共有はされていても、あまり意識されていなかった部分なんです。
林:私は人機官能という言葉ができた後に入社したのですが、学生時代にヤマハ発動機のことを調べていたとき、「MOTOROiD」を通じてこの言葉を知りました。「MOTOROiD」は2017年に発表された自律走行可能な二輪車で、搭載したAIにより、まるで生き物のように振る舞うことでオーナーとマシンが共響(きょうめい)するパーソナルモビリティのコンセプトモデルです。当時でも、機械に顔がついていて語りかけることで笑顔になる、といった擬人化的なコンセプトは見たことがあったのですが、「MOTOROiD」は言葉を交わさないコミュニケーションというところが粋で、精神的な「人と機械の一体感」を体現していると感じました。
一見矛盾することを両立することで、新しい価値が生まれる

—— そもそも「MOTOROiD」はどんなコンセプトから生まれたのでしょう?
末神:モーターサイクルを生き物化するというのがコンセプトです。もともとのコンセプトは、ヤマハ発動機のデザイン部門と技術開発部門、そしてアンドロイドの研究で有名な大阪大学の石黒浩特別教授の共同研究から生まれました。研究の中で、モーターサイクルを生き物化したらどんな世界になるのだろう、人間にとってどんな価値になるのだろう、ということを学術的に議論していたんです。そのコンセプトを具現化し、ヤマハ発動機が考えるモーターサイクルの未来という形で提案したのがMOTOROiDというわけです。
—— 末神さんは心理学のプロとして「人機官能」の考え方にどのように共感しているのでしょう?
末神:精神的な一体感も含めて人機官能を追求することは、学術的にも正しい方法だと思っています。モーターサイクルで風を切って走る体験は人の興奮を促し、交感神経系を刺激しますが、一方、リラックスして落ち着いた状態を作り出す副交感神経系の働きも人間には必要不可欠です。この副交感神経系の働きを促すのが、まさに精神的な一体感なんじゃないかと考えています。
人間って刺激にはいつか慣れてしまうものですが、リラックスし、落ち着いた状態には慣れというものがないんです。例えば、赤ちゃんと接するのは慣れるどころか、接すれば接するほど愛着が湧いて愛情がより深くなっていきますよね。そういった意味で、愛着が芽生えるような精神的な一体感をモーターサイクルに技術的に付加することができたらおもしろいだろうなと考えています。
—— 一聴すると相反する要素で、両立は難しそうに思えますが。
末神:確かに難しいですが、矛盾しそうなことを両立させるというのは、実はヤマハ発動機らしい考え方でもあるんです(笑)。レースの世界の話で、プロを目指しつつ趣味として楽しむみたいなこともそうですし、デザイン部門では相反する要素を対置することで、ヤマハらしさを打ち出す試みも行っています。また、会社が発行する最新の統合報告書では「感動」はエキサイトメント(高揚感)とエンパシー(共感)の両立であるとも言っており、異なる価値観や考え方を両立させるという試みは実は社内のあちこちにあるんです。ヤマハ発動機の社風のひとつと言ってもいいかもしれません。
MOTOROiDのコンセプトを紹介しています
「愛着」の可能性に着目
—— ヤマハ発動機らしい「人機官能」の両立の仕方とはどんな形だと思いますか。
末神:両立とは言ったものの、例えば身体的一体感と精神的一体感がある瞬間で同時に存在するというのはあり得ないとも思うんです。モーターサイクルを自分の身体のように操れることと、パートナーという自分とは違う存在に愛着をもつ、というのは矛盾していますから。そのうえで、状況によって入れ替わることで断続的に感動を生み出し、唯一無二の存在になっていくというのが、人機官能のめざすひとつの姿なのかなと、個人的には考えています。じゃあ、両立できる精神的な一体感って何なのか、そのあるべき姿を模索するのが、現在進めている愛着研究です。
—— 研究対象としてユニークであると同時に難しそうとも感じますが…。
末神:難しいですが、おもしろいですよ。例えば、研究の中で色々な人に「どんな物に愛着をもっていますか?」と聞くことがあるのですが、愛着というだけあって、皆さん思い入れがすごく強いんですね。「これはこんなに素晴らしいんだ!」「これだけが特別なんだ!」ってすごくパーソナルなエピソードを語るんですが、あくまで主観なので、客観的事実に基づかないことも多いんです。もちろん主観はとても大切なんですが、我々は研究として、それを客観的に納得できるよう、背景にある要因やメカニズムを抽象化・一般論化していかなければいけません。こういったことをヒモ解いてくことが人間研究の難しさであり、おもしろさでもあるのかなと思います。
「愛着研究が、将来ヤマハ発動機の新たな強みを生み出すかもしれない」
人機官能を追求する中で浮かんできた「愛着」というキーワード。分かっているようで曖昧なこの概念を解き明かすヤマハ発動機の「愛着研究」とは、どんなものなのでしょうか。研究を担当する長澤さんに聞きました。
-

長澤 美緒
クリエイティブ本部
ブランドマーケティング部
UI/UXデザイナー2013年ヤマハ発動機入社。入社以降は二輪のCMFG(カラーリング)デザインとメーターのUIデザインを中心に担当。現在ではデザイナーとしての経験や視点を活かし、人間研究チームの一員として日々研究業務に携わっている。
愛着という概念に対して、理解を深めていく
—— 愛着研究について、もう少し深くお話を伺いたいと思います。長澤さんはこの研究をどう捉えていますか?
長澤:昨今は色々なプロダクトが世の中に出てきています。しかし、どれだけ技術が進歩しても、市場が成熟するとスペック競争になっていき、結果として各社どの製品もどこか似たようなものばかり、というのは各業界に共通することではないでしょうか。そんな中で、スペック競争から脱する手段として愛着という要素を使えないかと思ったのがキッカケです。スペック競争では技術開発のコストが嵩み、ある種消耗戦のようになってしまいますが、愛着はそもそもスペックの高さのみで語れるものではありません。この愛着によって類似商品・サービスとの差別化を図ることができるとしたら、おもしろいものが作れるんじゃないか、と考えました。 MOTOROiDがもつ価値観は、まさに目指していきたい姿のひとつでもあり、今後、愛着研究でも取り扱っていきたいと思っています。
—— 愛着というカタチのないものを研究対象としていますが、具体的にどのように研究を進めているのでしょう?
長澤:愛着研究は昨年スタートしたばかりでして、現在は愛着に関わるさまざまな論文や書籍などを読み込んだり、社内で愛着に関連したワークショップを開催したりして理解を深めている段階です。いわゆる一般的な研究といったイメージですね。何か物を使っての実験をするというよりは、愛着という概念について、一つひとつ議論を重ねているところです。

「LOVOT」がくれた愛着のヒント

—— その中でも、ソーシャルロボット「LOVOT」の存在が愛着研究に影響を与えていると伺っています。
長澤:愛着研究が正式にスタートするより前に、「ロボットが身の回りにいる状態ってどんな感覚なんだろう?」「本当に愛着は芽生えるのだろうか?」とチーム内で話題になったことがあり、せっかくなら実際に体験してみよう、ということでオフィスの一角にLOVOTを導入しました。LOVOTは、「人に愛される存在として生まれたロボット」というコンセプトでGROOVE X社が開発したものです。 そういう意味で今回の研究にぴったりでした。導入前後でクリエイティブ本部内へのアンケートを実施し、ソーシャルロボット自体に対する価値観の変化を見たり、LOVOTと職場の雰囲気の関係性について観測を行ったりしています。
—— 何か発見はありましたか?
長澤:LOVOTのようなソーシャルロボットに対する印象が導入前後でガラッと変わったというのが印象的でしたね。LOVOTをオフィスに導入することは伏せた状態で「ソーシャルロボットに興味あるか」というアンケートを行ったところ、「少しある」が最多、「とてもある」「あまりない」という答えが次点で同数だったのですが、導入から数ヵ月経って再度アンケートを行ってみると、興味がないと回答した人の割合が全体的に減少し、興味があると回答した人が増えました。一方で、数は減ったものの「全く興味ない」と答えた人も変わらずおり、別の質問項において、実際にLOVOTと触れ合うことで反応が二極化したことを表すような結果が得られました。あまり興味のない物事であっても、自分で触れて体験することで個人の価値観は変わるということが可視化されたのは興味深かったですね。こういった実証実験の結果も、愛着という感情をヒモ解く、ひとつのヒントと言えます。

—— 個人差が大きいがゆえに、研究で得た知見を製品に落とし込んでいくことは難しそうに思いますが…。
長澤:そうですね。ただ、もともと愛着というキーワードは社内でも頻繁に出ているものなので、製品やサービスに落とし込んでいこうという動き自体は活発です。例えば、コスト面や品質管理面での問題さえなければ製品の素材を本革にする、みたいな発想で愛着を感じさせる要素を実装していくことはできると言えます。とはいえ、人がどんなものに愛着をもつかというのは、もっと多様で複雑です。今後、愛着の研究を続けていけば、どんどん難しい問題に直面していくはず。その問題を一歩ずつ深掘りしていくことで、愛着の種となるような要素がたくさん見つかると考えています。その中で、技術やスペックにこだわらずとも愛着を感じてもらえる手法が見つかれば、既存のさまざまな製品やサービスに反映していくことができるのではないでしょうか。
—— 最後に、今後の展望を教えてください。
長澤:研究自体はまだまだ発展途上ですが、今後続けていくうえで重要になると思っているのは、たくさん見つけた愛着の種のようなものを、どう整理してヤマハ発動機らしい概念として統一していくかというところ。それがどんなカタチになるかはまだ具体的には見えていませんが、私個人としては、ヤマハ発動機の製品はユーザーに価値観を押しつけるものではなく、ユーザーと相互に関係性を育んでいくものであってほしいと考えています。そのことを忘れず、一人ひとりに唯一無二な存在であると思ってもらえるような製品やサービスを、愛着研究を通して作っていきたいです。