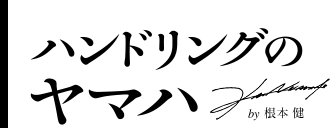XS-1からXJ650へ。ビッグバイクハンドリングの礎。
'70年代に初の4スト・ビッグバイクへのチャレンジでライバルがこぞって4気筒エンジンを開発するなか、ひとりビッグツインにこだわったヤマハ。650ccのXS-1にはじまってTX750、TX500と次々に新機種を投入したがヒット商品とはならなかった。しかし、ただでさえむずかしいビッグツインのハンドリングと取り組んだ結果、いち早く剛性などシャシー開発のノウハウを得るという貴重な時期でもあったのだ。'76年の3気筒GX750を経て遂に他と同じ4気筒開発に着手したヤマハは、そこで他に先んじたシャシーのノウハウを集約するカタチでXJ650を開発、その群を抜いたバランスの良いハンドリングで「ハンドリングのヤマハ」神話を復活させたのだった。このパーフェクトで感性豊かな乗り味は、ヤマハ・スポーツバイクのハンドリングの基礎となり現在まで受け継がれている。既に創刊3年目を迎えていたライダースクラブのインプレも交えながらその不滅の傑作車XJ650の魅力に迫る。
(以下、本文は1996年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)
根本健
1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。
16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。
現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。
ビッグバイクのむずかしさと真剣に取り組む
ライバルの4気筒勢に負けまいと開発したNewビッグツインTX750、TX500が不人気に終わった後も、継続して改良の手を緩めなかったバーチカルツインXS-1(ネーミングはTX650に変更されていた)。しかし、このバイクが残した車体関係のノウハウなくしてその後のヤマハのビッグバイクはあり得なかったと言っても決して過言ではない。
当時、僕はそれまで所属していたカワサキ系チームを出てプライベート・チームを結成、それまでワークスライダー以外はレースでプロとして飯が喰えないという状況にチャレンジを開始していた。賞金もろくに出ない状態だったので、スポンサーを獲得する一方、関連産業の開発テストに関わるという副業が必要で、ラッキーなことにタイヤメーカーからテストライダー兼エンジニア的な仕事を請け負うことができたのだ。
その頃、日本のバイクメーカーは初のビッグバイク・チャレンジでどこもハンドリングに悩まされていた。無理もないのは、ほとんどスタイリング・スケッチを先に描きそれに従って車体を設計していたのだから、たとえばエンジンの搭載位置も重心が低い方が安定性が高いであろうという程度はわかっていても、これとホイールベースやアライメントの関係などのノウハウは皆無に等しかったからだ。250ccクラスならそれでも通用したが、4ストのビッグバイクともなると200kgを越える重い車重とエンジンの強大なパワーは、真っ直ぐ走ることさえむずかしくする。ましてや市販車で200km/hという、ビッグバイクの先輩メーカーである海外ブランドも未踏の領域に達しようとしていたのだからなおさらである。
各メーカーは剛性などシャシー改良もさることながら、それまで重視していなかったタイヤやサスなどの性能にこだわりはじめたのである。これら機能パーツは、下請けメーカーがアッセンブリー・メーカーの指示通りに造ってライン装着用に大量納品すれば良いという図式だったが、バイクメーカーから各々のパーツメーカーに対し、独自の技術力の構築の要求がはじめて下されたのだった。
そうした背景があったからこそ、僕はタイヤメーカーの開発テスト業務にありつくことができたのだ。
タイヤメーカーにしてみれば、それまで車重や馬力などバイクメーカーから指示されたスペックで最大荷重を設定したタイヤに、バイクメーカーのテストライダーからの改良要求を加えれば事足りていたライン装着(OEMという)タイヤの開発に、いきなり独自の技術構築をせよというのだから実に大変な事態になったわけだ。
しかし、僕にしてみればバイク用タイヤの基礎から学ぶ絶好のチャンスでもあった。市販車用のOEMタイヤの開発から国産初のレーシング・スリックタイヤの開発まで、創成期ならではのやりがいのある毎日を送ることができたからだ。
そのなかで量産車用OEMタイヤ開発で最も印象的だったのが、他ならないこのヤマハTX650だったのである。タイヤメーカーとしては、どのバイクメーカーともOEMタイヤ開発でつきあうが、ヤマハが中でもハンドリングに最もシビアだった。そのヤマハがビッグバイクのシャシー開発のノウハウを賭けて取り組んでいたTX650のテストの物凄さといったらない。しかし、その真剣さに僕とタイヤメーカーのエンジニア・チームは感銘を覚えた。ここでヤマハと徹底的につきあっておけば、ビッグバイク用タイヤ開発のノウハウもいち早く手に入る……。そう判断したチームは、ヤマハからの要求をすべて受け入れることにした。

根本健氏(後列右側) 1973年フランス・マニクールサーキットにて
1973年のMFJのMVPを獲得し、 その特典として授与された世界一周チケットにて旅行中の一葉。前列左端が毛利良一選手、左から3人目がパトリック・ポンス、右端がオリビエ・シュバリエ
ウォブル対策の強烈なテスト方法
そのひとつが、ヤマハが独自に行なっていた特異なテスト方法と同じ状況を、こちらでも再現することだった。それはウォブル・テストの一種で、大きな鉄板の上にスロープ状の舗装を施し段差をつけたものを製作、これをテストコースの直線や高速コーナーに置き、バイクで140?160km/hの猛スピードで乗り越えるというのである。
ヤマハはこれを袋井テストコースに持ち込んでテストしていたが、我々も同じものを製作、富士スピードウエイでテストをした。TX650を140?160km/hまで加速させて、この架設段差に突っ込むとバイクは一瞬何かに突き当たったような衝撃を食らう。前輪の通過でハンドルが左右に大きく振られ、直後に後輪からの突き上げで車体全体が大きく揺れる。ガツン!、グラグラッ、ユラユラユラ……。慣れるまでは生きた心地がしなかった。これが直線だけならまだしも、高速コーナーでバンクしたまま突っ込むのである。傾いた車体にキャスター角のついた前輪とくれば、衝撃と化す段差で当然ハンドルが左右フルロックまで大きく振られ、前輪がキャキャッと鳴く始末。転倒寸前を何度も体験した。
しかし、後輪を減衰特性の良いダンピング吸収の効いたカーカス構造にまとめていくと、このユラユラが数回で収まりはじめた。前輪も剛性の均一な構造となるよう工夫を凝らすうちに、いわゆるウォブルの起きにくいバイクにTX650は変わっていったのである。最終仕様はドイツのアウトバーン走行で安定感が最もあると評価されたメッツラー製と同じ、レーヨン・コードをカーカスに採用した。なぜレーヨンが必要だったかというと短繊維という特徴のためである。簡単にいうと、一番使われるナイロンは長繊維でタイヤの内圧でピンと張ったトコロに衝撃が加わると全体がビーンと共振するのに対し、レーヨンの短繊維は衝撃が加わった箇所だけでドスッと吸収してタイヤ全体に振動を伝えないという差があるからだ。原理的にはアコースティック・ギターの6本の弦のうちナイロン弦の高音側3弦が1本の長繊維で、低音側3弦がワイヤーの中に短繊維を使うのと同じである。高音は弦全体がいつまでも振動しているのに対し低音が短時間で減衰するのはギターを弾けなくてもご存じのはずだ。
しかし日本でタイヤのカーカスに使う工業繊維は、ナイロンとポリエステルが主流でレーヨンは既に存在しなかった。そこでヨーロッパからわざわざ高価なレーヨン・コードを輸入したといういわくつきのタイヤなのである。

TX650
XS-1のバーチカルツインエンジンと優美なスタイリングを継承しながら、新設計フレーム、高剛性スイングアーム、H型アルミリム、減衰特性を見直した前後サスペンションなどの採用により、走行性能・特性を大きく向上させた(1973年発売)
ひたすら安心できるハンドリングを求めて
また問題は高速で車体が揺れるウォブルだけでなく、アメリカ西海岸に多いレイングルーブ対策にも及んだ。レイングルーブとは一気に多量の降雨があったとき、路面に水膜ができてタイヤが全くグリップしないハイドロプレーン現象が起きるのを防ぐため、路面の縦方向に溝を彫ったものだ。これはクルマの通常の運転では影響がないが、バイクだと前後輪がこのグルーブ(溝)にタイヤをとられた感じがして、ライダーがパニックに陥ることがあるという厄介なシロモノなのだ。当時の日本には高速道路では東北道の那須近辺にこのレイングルーブの試験舗装路があり、タイヤのプロファイルやパターンの形状やピッチまで変えた試作タイヤで何度となく那須まで出かけて走行テストを繰り返した。
ヤマハの要求が、こうした特殊な状況だけでなくハンドリング全般に及んだのはもちろんのこと。自社でピボットまわりの剛性を高める試作やアライメントの追究を繰り返しながら、タイヤメーカーにも癖のないハンドリングを要求し続けた。偏平になりはじめた後輪のプロファイル(断面形状)に対し、前輪のラウンドしたプロファイルやアライメントとのバランスをとることで乗りやすさが得られるといったノウハウもこの時期に構築されたものである。
しかし、さらにヤマハの要求はシビアさを極めた。日本製OEMタイヤは、新車の頃の1,000km程度は初期のハンドリングやグリップを得られるが距離を走ると偏磨耗して性能が急激にドロップするというのだ。それは事実だった。プライベートで世界GP遠征をはじめていた僕は、レースの合間やシーズンオフにヨーロッパで試作タイヤ毎に交換しないままアウトバーンなど3,000kmをTX650で走り切り、仕様の違いを確かめるというテストまでした。
このヤマハの安心して乗れる素直なハンドリングを中途半端なところで妥協せず追究する姿勢に、僕は心うたれた。正直言って、当時の他のメーカーはここまで徹底していなかったからだ。大抵は限界まで攻めたときのグリップと、ハンドルが振れなければOKだった。
(後編へ続く)

1973 東京モーターショー出展
1973年の東京モーターショーで、TX650はTX750/500とともに「TXシリーズ」として同時発表された