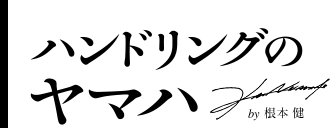Vol.3 4ストロークへのチャレンジ ビッグツインへのこだわり
'60年代初頭からの世界GPチャレンジで見事タイトルを獲得し、スポーツバイクのヤマハを世界に知らしめた’60年代末期、日本メーカーもビッグバイクのカテゴリーに挑戦を開始し、二輪車開発激動の時代に突入していく。2ストロークが主体だったヤマハも、当然、4ストローク・エンジンの重量車開発というテーマに取り組むことになる。他メーカーがこぞって4気筒エンジンの開発に心血を注いだのに対しヤマハはビッグツインにこだわった。軽量、ハイパワーなバイク作りを得意とするヤマハが、独自路線で世界を目指すのは自然な流れだったのだろう。しかし、ツインエンジンで4気筒に対抗できるマシンを目指したことがハンドリングをむずかしくしてしまい、ヤマハのピンチを招くなどと誰が想像できたであろうか……ライバルに追従せず、ビッグツインで苦しむことになるが、結果として早くからハンドリングを学ぶことになり、レーシングマシンで培ったハンドリングのノウハウは、ストリートの4ストローク・ビッグバイクにも受け継がれていったのだ。
(以下、本文は1996年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)
根本健
1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。
16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。
現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。
アメリカ市場を狙った大型車開発がはじまる
まだ日本のメーカーが世界GPに血道をあげていた'67年、ホンダは初のDOHCヘッドをもったはじめての大型車、バーチカルツインのCB450を発表した。CB72とCB77(250ccと305cc)で世界にスーパースポーツのメーカーとしてイメージを確立した後の次のステップへチャレンジを開始したのである。またカワサキも、吸収したメグロのOHVバーチカルツインを650までスケールアップしたW1を投入、2スト3気筒500のマッハⅢと共に大型車マーケットに参入を開始したのだった。
実は'60年代以前のバイク黎明期において、いくつかの日本メーカーは500ccやそれ以上のビッグバイクを生産していたのだ。しかしそれは英国車やドイツ車のコピーで、高価で希少な輸入車を買えない国内ユーザーに向けた商品で、性能的にも輸出できるシロモノではなかったのだ。
それが'60年代後半になって再び大型車へのチャレンジをはじめたのは、いうまでもなく海外の市場を睨んでのことだ。それもアメリカに照準を据えてのことなのである。'60年代から'70年代のアメリカは、バイクメーカーにとって最大のマーケットだった。若者は英国のトライアンフやBSAなど650ccクラスのビッグバイクを乗りまわすことが流行で、これに乗じようとBMWもアメリカ・ナイズされたカラーリングの750ccを投入していた。

1970 XS-1
ヤマハ初の4スト・ビッグツインXS-1。英国車の路線を選んだスタイリングで'70年のデビュー。空冷SOHCのバーチカル・ツインは75mm×74mmの653cc。圧縮比9.0で53PS/7,000rpm。5段ミッションと185kgの車重で最高速度185km/h。XS-1はTX750やTX500が短命に終わった後もTX650として継続して改良が加えられ、さらにアメリカン・スタイルのスペシャルというシリーズに転用されて記録的な長寿バイクとなった。
250ccや350ccの価格でビッグバイク並みの高性能が得られた日本車だったが、次第にエスカレートしていくアメリカ市場に向けて本格的なビッグバイク開発が急務と決断していたのである。これを決定的にしたのが'69年のホンダCB750フォアのデビューだ。GPレーサーだけのメカニズムと思われていた4気筒エンジンが、大量生産されるスーパースポーツに搭載される……アメリカだけでなく全世界が色めきたった。
そして続くカワサキのZ1はCB750フォアの登場で、750ccを開発していたのを急遽900ccまでスケールアップ(国内向けはオリジナルの750ccZ2となったのはご存じの通り)してデビュー。日本メーカーはこれを機に一気にビッグバイク時代へと突入したのだった。遅れをとるまいとヤマハもビッグバイク開発に着手した。しかしはじめての4ストローク・エンジンという大きな壁が立ちはだかり、'80年代を迎えるまでの間、ヤマハのビッグバイク開発は何年間も紆余曲折のときを過ごすのだった。
ひとつには商品開発のコンセプトにむずかしさの発端があったといって良いだろう。他メーカーがこぞって4気筒エンジン開発に走ったのに対し、ヤマハはアメリカで人気の英国車と同じバーチカルツインに手を染めたからだ。現代のノウハウからみれば、ビッグバイクのツインはハンドリングにむずかしさの出やすいカテゴリーであることは容易に判断がつく。英国車のようにエンジン性能に多くを求めようとせずに軽快なハンドリングのバイク……で済ませるのならまだしも、ライバルに4気筒を睨みながらパワーもトップスピードも稼ごうとすれば、スリムでも重心が高くなりがちなバーチカルツインで安定したハンドリングを得るのは至難の業だからだ。
ビッグツインに苦しみながらノウハウを得る
ヤマハ初の4スト・ビッグバイクはそのバーチカルツイン、SOHCで650ccのXS-1で'70年に登場した。英国のトライアンフやBSAのイメージに触発された美しいスタイリングのバイクだったが、開発段階においてはハンドリングに悩まされた。「XSの開発は当初エンジンが目標性能に至らず、まずエンジニアはこれに没頭していました」。当時を振り返って藤森孝文氏(故人)が事情を説明してくれた。(第2プロジェクト開発室・実験担当・主任技師:インタビュー当時)
「当時よくベンチも見に行きました。2ストのように吸排のポートじゃなくて4ストはカム・プロファイルだよと、熔接でカム山を大きくしてグラインダーで削ったり……ホントに手探りだった」。
そうこうしているうちに何とか目標性能に近づきバイクが走りだした。ちょうどその頃、ヤマハは袋井テストコースが竣工する。この高速で直進からコーナーまでテストができるコースのおかげで、ヤマハのバイクはあらためてハンドリングの良さで定評を得ていくのだが、XS-1ではまだそれ以前の段階だったのはいうまでもない。 「最初は140~150km/hくらいのテストで操安(操縦安定性)もこの速度域だった。その後180km/hあたりまで高くなるんですが、開発当初はこのレベル。これだと特に問題は出ない。それが性能が上がって速度が出てくるとハンドル振れを起こしはじめた」。

XS-1開発時を振返る藤森孝文氏(1996年)
いわゆるウォブルと呼ばれる振れで、どんどん増幅するケースが多く、だからといって急激にスロットルを閉じると、揺れていくぶん逃げていた応力が一気に反力として集中し、もっと激しくハンドル振れを誘発して転倒しかねないというものだった。
「エンジニアのところ行ってエライ振れるゾ、と報告した。相手もはじめてのことだから、じゃどうする?と問い返すしかない。そこで揺れているんだから強度が足らないんだろうと、エンジン・マウントからスイングアームのピボットを作り直してみた。フレームにもクロスパイプやガセット(パイプの組み合わさるコーナーを補強する平板)を熔接して剛性アップをはかったんです」。 「すると、オイ何だか硬くなったなァ、という感じで違いがわかってきた。市販車開発で操安を技術として根本から取り組んだのはコレがはじめてといえるでしょうネ。問題が大きなバイクが出てきたからこそ、取り組まざるを得なかったわけで、そういう意味では早くにそうなって良かったということを後でつくづく思うわけです」。
当時は、はじめにデザインありきで次にエンジンのカタチが決まってそれからテストがスタートしていた。いまのようにあらかじめ技術的に問題が出ないよう車体のスペックを決めておいて、などというノウハウはなかったから無理もない話しだ。また性能的にもハンドリングなどについても、目標を先行ライバル車に置くしかなく、相手がこのくらいだからコレで良いか、というのが判断基準だったそうだ。そういう意味ではトライアンフもBSAも高速でウォブルは出ていたから、XS-1も開発初期段階ではそれほど深刻にうけとめていなかった。(後編へ続く)

1972 TX750
TX750はヤマハ初の750ccロードスポーツ。並列2気筒エンジンならではの独特なトルク感と鼓動感、スリムな車体による軽快な操縦性を実現した(1972年発売)

1973 TX500
ヤマハ初のDOHCエンジンを搭載したロードスポーツTX500。足まわりにはアルミリム、フロントディスクブレーキを裝備し、スポーティな走行性能を発揮した(1973年発売)