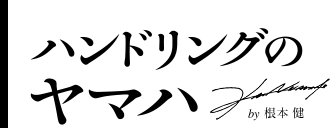Vol.5 レーシングDNAの発動。 スーパースポーツのマイルストーン、 TZR250。
'80年台に入ってからのヤマハは4ストローク4気筒の傑作車XJシリーズで「ハンドリングのヤマハ」のイメージを取り戻しただけでなく、排気ガス規制などでスーパースポーツとしては命絶えたとまで言われた2ストを、RZ250で復活させるなど一躍活気を帯びてきた。このRZ250をきっかけにライバル・メーカーから2スト・レプリカが続出、「ハンドリングのヤマハ」を象徴する1台でもあるTZR250が誕生したのだ。TZR250はヤマハが誇るレーシングマシンのエンジニアによって開発されたのが大きな特徴で、当時のワークスマシンのノウハウがダイレクトに反映されていた。なかでも当時500ccのGPマシンはそのハイパワーとハンドリングの両立に苦しみ、YZR500の開発テーマも“人間の感性とのバランス”という現在と同じ領域に到達していて、エンジン特性もハンドリングも基本特性を大切にして過渡特性を滑らかに扱いやすくというYZRそのままの考え方がTZRにも注ぎ込まれていた。
(以下、本文は1996年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)
根本健
1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。
16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。
現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。
ビッグバイクのむずかしさと真剣に取り組む
遂にライバルと同じ4気筒エンジンを採用し、4ストロークのスーパースポーツでも肩を並べるどころか、名車XJ650とXJ400により一躍他をリードするところまで完成度を高めた。両車がデビューした'80年、ヤマハは2ストロークの方でも歴史に残るエポック・マシンを発表した。RZ250である。
それは排気ガス規制などで将来がないと言われていた、2ストローク・スーパースポーツの復活宣言といえるものだった。それというのも'76年のRD400が4ストロークを意識してかエンジン特性も穏やかで、本来の2ストの魅力であるアグレッシブなフィーリングを感じさせるものではなかったからだ。既にスーパースポーツとしての2ストは命絶えた……そう囁かれはじめていたのである。
しかし、レース・シーンではヤマハのイメージ・リーダーとして市販レーサーTZ250やTZ350をはじめYZR500ワークスマシンやTZ750が活躍していたのだ。もともと2ストローク・メーカーだったヤマハを知るファンにとって、このイメージをそのままカタチにしたようなバイクが切望されていたのは間違いなかった。ヤマハでも何とかこの期待に応えよう、2ストを今後も活かそうという意気込みで、レーシングマシンと同じ水冷エンジンを採用した新型2スト・スーパースポーツの開発がスタートしたのである。

RZ250
2ストローク本来の軽量・俊敏な加速感と軽快なフットワークを磨き上げたピュアスポーツRZ250。そのスタイリッシュなデザインとともに大きな話題となり、一躍大ヒット。衰退しつつあった2ストロークモデル復権のきっかけを作った(1980年発売)
このプロジェクトは、輸出用ではRD350LC、国内向けはRZ250としてデビュー、とくに日本国内のバイクブームにTZレーサーのレプリカというイメージが加わってRZ250は大人気車種となった。本来の2ストらしさを大切にしたピーク域の鋭さと中速域のトルキーなフィーリングに、多くのファンが酔いしれたのはいうまでもない。これに刺激されたライバル・メーカーが追いかけるようにしてこぞって2スト250レプリカを開発、その後のレプリカ時代を生むきっかけとなったわけだ。
もちろんそのハンドリングも高い評価を支える一因で、扱いやすい安定性をベースに軽快でシャープなフィーリングが味わえるようにと、いかにもヤマハらしいまとまりをみせていた。レース・シーンで圧倒的な強さをみせてきた市販レーサーTZ250・350を開発してきたヤマハにとって、1本のショックユニットとしたリヤのモノクロス・サスペンションの採用や車体の剛性など技術的に問題なく、例によって実用域での味つけという感性のレベルでこだわる完成度の高さを誇っていたのだ。この誰でも楽しめるハンドリングに、大成功を収めたXJシリーズと共に「ハンドリングのヤマハ」イメージが当然のように思われはじめたのもこの頃からだ。しかし、本当の意味での「ハンドリングのヤマハ」としての闘いは、この後に正念場を迎えるのだった……。

RZ350
ヨーロッパでは350ccのRD350LCが発売され、ワンメイクレースも大盛況。瞬く間に大ヒットモデルとなった
人間の感性をテーマとする新しい次元に突入
2スト・スーパースポーツを復活させたRZシリーズは、その後'84年に4気筒のRZV500Rが登場するというエスカレートぶりをみせた。しかし'85年にデビューしたアルミ・デルタボックス・フレームを採用したTZR250は、単にレプリカ・ブームの延長線上で語るのではなく、別格扱いをしておく必要があるだろう。それは2スト・スーパースポーツとしての進化だけでなく、4ストのビッグバイクまでを含めた最新スーパースポーツのハンドリングの方向性に多くの影響を与えたバイクとして、重要な意味をもつ存在だからだ。
TZR250開発プロジェクトは、当時のロードレース・ワークスマシンのエンジニアが開発に直接従事したというところがそれまでのヤマハ他車との大きな違いであった。プロジェクトリーダーの阿部輝夫氏(当時の第2プロジェクト開発室・プロジェクトリーダー)の所属していたレースグループの中に、市販車の開発メンバーが加わるというカタチをとったのである。その結果、TZR250は当時YZR500で採用されたばかりのアルミ・デルタボックス・フレームを採用するという正しくYZRレプリカとなったわけだが、ここで別格扱いをする理由はいかにYZRをコピーできたかではない。
それはTZR250にYZR500のハンドリングに対する考え方が反映されていたからだ。なぜそれが重要なのかは当時のYZR500が歩んだ道を辿る必要がある。

1982年型YZR500(0W61)
GP500初の2ストローク・V型4気筒エンジン、進化したアルミフレーム、車体下・進行方向横向きに配したリアサスペンションなど独自機構が数多く投入された。市販スーパースポーツRZV500R開発のベースとなったモデルでもある
'60年代の多気筒多段ミッションのGPマシンを、日本の他のメーカーと同じく世界GPから撤退させたヤマハは、ひとり'70年代も市販レーサーで途絶えることなくレースシーンに関わってきていた。そして'73年に初の500ccクラスにワークスマシンYZR500を投入して完全復帰を果たしたのだった。
型式名0W20と呼ばれた初のYZR500は、並列2気筒を横に連結した並列4気筒という特異なエンジン型式を採用していた。これは実績のあった250ccツインを活かすこと、それに市販車にも開発のノウハウをフィードバックできる可能性を持たせるのが狙いだったからだ。この手法はその後TZ350を同じように横に連結したTZ750でも継承された。
しかし、さすがにワイドになってしまう並列4気筒エンジンに、
名手ケニー・ロバーツをもってしても'81年以降はスリムでコンパクトなスクエア4エンジンのスズキRG500γや3気筒ホンダNS500の軽快なハンドリングに対抗しきれなくなったのである。そこでヤマハも'81~'82年にスクエア4に続いてV4エンジンを開発、一気に差をつけようとしたのだが、ここで大きくつまずく結果となったのだ。
これは過去弊誌がYZR500を特集したときに、歴史に残る逸話としてワークスマシンを開発したスタッフが敢えて告白してくれた貴重なストーリーでもある。それは500ccエンジンをコンパクトに収めるため、250ccツインを前後・連結のスクエア4から上下・連結したV4エンジンをはじめて搭載した型式名0W61というマシンについてだ。
スペック的に優位と思われるすべてを注ぎ込んだ0W61は、乗り手であるキング・ケニーと呼ばれた天才的名手K・ロバーツの意見に従って開発されていた。たとえばRタイヤは可能なかぎりワイドにという要望に、タイヤ・メーカーと超ワイドなレーシングタイヤを開発したのだ。年々パワフルになっていく500ccを自在に操れる数少ないひとりだったキング・ケニーにしてみれば、絶対的なグリップ力さえあればコーナリング中にもっとパワーをかけられるとイメージしたからに他ならない。自分ならコントロールできそうな折角のパワーを、Rタイヤが滑りはじめてしまうため活かしきれない……というわけだ。
しかし、当時はいまのようにワイドでも軽快に乗れるラジアル・タイヤが開発される前で、スペシャル・オーダーで超ワイド・リムに装着されたバイアス構造の超ワイド・タイヤは、トレッドの展開幅が広い分リーンをしていくときにリーンを極端に重く遅いものにするという、さすがのキング・ケニーにとっても乗りづらいハンドリングを生むだけだった。
エンジン特性にしても500ccを乗りこなす余裕さえあったケニーにとって、普通のライダーならコーナリング中に頼る中速域を自分ならピーク域に維持したままコーナリングできると考え、とにかくピーキーでも良いからパワフルにして欲しいとの要求に応えたのだという。が、いざレース・シーズンがはじまってみると、実際はタイヤの件も含めてケニーでさえ中速域を多用せざるを得ない状況が多く、ストレートは最速でも脱出加速で逆に遅れをとる結果となってしまったのだ。
さらにシャシー剛性でもスクエア4で高速のデイトナにチャレンジするときに、高速コーナーの高荷重を想定してフレームにクロス・メンバーを追加する超高剛性シャシーとしたところ、シケインで曲がらないハンドリングになってしまい、慌てて現地でそのクロス・メンバーを切り落としたという経緯もあったとのこと。
“常人では想像できない領域でライディングするキング・ケニーの言うことなのだから、常識を持ちださずにやるだけやってみよう”という目論見は、見事に外れたというわけだ。
感性に馴染みやすい基本特性を追究する
この貴重な経験をベースに、ヤマハのワークスマシン開発のエンジニア達が胸に刻んだのは“すべての特性を人間の感性に馴染みやすいものしなくては”というものだった。
そこで次のモデルである0W70ではエンジン特性において、やみくもにピークパワーを狙うのではなくピーク域をいくらか犠牲にしても、中速域から連続してなだらかなパワーが得られる特性としたのをはじめ、シャシーも高剛性でありながらしなやかな特性を狙うなど、レーシングマシンというより一般のロードスポーツを開発するときと変わらないようなテーマと取り組んだのである。
とくにフレームに関しては、従来までのアルミ角断面パイプの構成でどのようなカタチが構造的に強靱かのノウハウをベースに、応力がかかったときに適度にしなるようこのカタチをパイプではなくアルミ板でつないだデルタボックス・フレームをはじめて採用したのだ。
(後編へ続く)


TZR250開発プロジェクトリーダー阿部輝夫氏
(第2プロジェクト開発室 1996年当時)