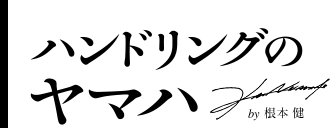難しい局面でレーサーの顔をのぞかせるハンドリング性能
(前編より続く)
モーターサイクルのサスペンションは、一連のコーナリング・アクションで減衰力が強いとハンドリングを重く感じさせ、弱めれば軽快感を得られるのだが、これに安定感も伴いたいためどこかで頃合いに設定しなければならない。しかしERS(電子制御サス)だと、このようにそのときの減速度や車体の姿勢や挙動、それにスロットル操作による加速度などの状況次第で、欲しい状態へリニアに変化してくれるのだ。
一番わかりやすいのがヘアピンだった。ヤマハテストコースは、手前で右に曲がりながら左のヘアピンへアプローチするのだが、減速しながら右にリーンした車体を最後の減速で一瞬直立させるそのときに、さらに強いブレーキングを与えても過度なノーズダイブとならないため、左へターンをはじめるきっかけが前のめりでない分、通常のコーナーと変わらない後輪を軸にした旋回にできる。クロスプレーンのクランクのおかげで、エンジンブレーキの収まりが良く、リーン直前の慣性力を残した重さが全くない。低い速度とスロットルを閉じた状態にサスの減衰力が弱まり、軽やかでフラつかないスムーズな旋回となる。

その極みがそこからスロットルを開けるシーンだった。低速で車体が安定していないヘアピンのスロットル操作は、開けた瞬間のレスポンスがちょっとでも唐突さを伴うと車体が揺れてしまいがち。だからライダーは最初に駆動がはじまる瞬間をスムーズにしようと、丁寧かつ慎重に探るような操作でスロットルを開ける。しかしR1Mはここもクロスプレーン効果で、気がついたら後輪が路面を蹴りはじめているというスムーズさだ。むしろやや早めに大きく開けたほうが、後輪が路面を掴んで曲がるチカラを引きだしやすいことに気がついた。
走るほどにこうした状況変化に対応してくれるポテンシャルが身体に馴染み、試乗前の緊張はどこへやら……徐々に大胆な操作へと駆り立てられていった。テストコースということで、中速以上のコーナーをリーンしたまま全開も試みたが、後輪がややスライドした状態をキープして旋回加速を続けていくその醍醐味にすっかり魅了されてしまった。
ただ長い下りのストレートを300km/hの領域で矢のように突進していく凄まじい世界だけは、緊張の連続で楽しいとは思えなかった。いくらカウルに身を潜めようが、前方からの風圧は避けられても頭から背中にかけて後ろに引っ張られる強い負圧に、ハンドルにしがみつき上半身から腰まで力を込め続けることになる。サーキットのストレートは、コーナリングで疲れた身体を休める区間という昔の常識は、いまや通用しないことをいまさらながら痛感させられた。
人間の感性にシンクロする電子制御技術はいかにもヤマハ的
素晴らしい! 賛辞のあらんかぎりを口にして、新世代のハンドリング開発のフィロソフィーについて聴くべく、実験グループ主査田中陽氏へのインタビューに臨んだ。前回でお伝えした1998年初代YZF-R1の開発では、ライバルの思いきった鋭いハンドリングの魅力を認めながら、その領域に対するヤマハの方法論の違いを立証、全世界にR1ファンを生み出す結果となったのはご存じの通り。そしてヤマハにとっての新たな領域で、より完成度を高めるための進化もとどまることを知らなかった。2000年には早くもエンジンから車体まで全面改良を施した2代目が登場、2002年にフューエルインジェクション化と車体バランスを見直した3代目といった按配で、2015年の8代目へと進化を重ねてきた。
この間、2009年のクロスプレーン化というMotoGPマシンYZR-M1開発からのフィードバックもあり、究極の世界が目指す方向へターゲットを絞り込んではいたが、今回のハンドリング全体を革新的に進化させたといって良い飛躍がどのようなプロセスで生まれたのかを語ってもらった。

新設計アルミデルタボックスフレーム(YZF-R1)
MotoGPの開発思想を受け継ぐニューフレーム。縦、横、ねじりの剛性バランスの妙が、エンジン特性と相まってこれまでにないリニりティを実現。ブレーキもコントロール性と絶対性能を大幅に向上させた

インタビュー動画にあるように、先ずはMotoGPマシンYZR-M1に実際に乗ってみることからスタートしたそうで、GPライダーにしか扱えない領域さえイメージできる、その乗りやすさの要因をピックアップしてきた由。暴れまくるマシンに蛮勇をふるう世界にしか見えないかも知れないが、実はマシンの一挙手一投足の過渡特性、つまりパワーや車体の挙動がはじまるそこの特性変化を如何にライダーが馴染みやすいものにするか、そこに集中して開発されているのを確認したとのこと。やはり乗ってみなけりゃわからない世界だったという。
これを市販車に具現化するため、エンジンは出力特性やコンパクト化のみならず、車体の挙動と関連した形状から搭載位置、そして車体も加減速で求められるアライメントから剛性バランスに至るまで基本設計を刷新、実際に走行しながら諸々の設定を煮詰めていったのだ。
そこで重要なのがYRC(ヤマハライドコントロール)と呼ばれるエンジン特性など、状況に応じて変化させるデバイス。詳しくは専門誌などをご覧頂くとして、エンジン回転数やミッションの段数にスロットル開度だけでなく、ジャイロセンサーとGセンサーによって車体のピッチ・ロール・ヨーの3方向、前後・左右・上下の3方向の、6つの動きを検知してコントロールに反映しているのである。R1MではこれにERS(電子制御サスペンション)と各種設定をライダーがセットで選べたりマニュアルに個々を調整できるCCU(コミュニケーション・コントロール・システム・ユニット)が搭載され、お伝えしたような夢のライディング・パフォーマンスを自分のモノにできるのだ。
こうしたデバイス技術の話しになると、徹底した解析で答えが得られるように錯覚しがちだ。が、それは間違っている。これまで連綿と人間の感性に馴染みやすいハンドリングを追求してきたヤマハだけに、解析はしても実際の変化量などの設定に、これまで積み重ねてきた人間の感性にシンクロさせるこだわりが活かされている。
たとえばライダーはそのスキルによって、どこを不安や不都合に思うかが異なる。この様々な想定を可能な限り繰り返し試すことに、走行テストの多くを費やした。如何に不安なく、如何に意図に遅れることなく、思い通りに走れるかをプロからスポーツユーザーまで幅広く検証したそうだ。しかしどの話しをしようと、ライダーという人間に必要なちょっとしたラグ、言葉にするとジワッとかやんわりとか、いわゆる過渡特性の味付けに帰着するのがヤマハらしい。どんなにハイエンドを求めても、マシンにライダーが乗せてもらっている状態はヤマハではNGなのだという伝統が確実に守られていたのは嬉しかった。
それがMotoGPマシンYZR-M1でも同じ……ボクを含めて誰しも俄には信じられないに違いない。そこへYZR-M1に乗れますよ、というとんでもない知らせが入った。我が耳を疑うあり得ないチャンスは、あろうことか実現したのだ……(次号へ続く)。


田中陽氏 実験開発グループ主査
歴代YZF-R1の操縦安定性を作り込んできた開発ライダー。全日本選手権や鈴鹿8耐などで活躍する社内チーム「磐田レーシングファミリー」でリーダー役を務めた