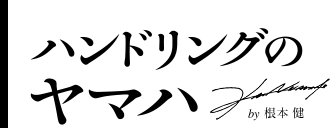Lap#2 緊張は薄れ、徐々に大胆になってくる自分がいる
(前編より続く)
アッという間の第1コーナー。超弩級のストッピング・パワーだが、不思議なほど安心感を伴うのを知ってからのブレーキングなので、内心ダイジョーブ?と脳裏をかすめつつ、もうひと息奥まで突っ込んでからブレーキレバーへ入力。今度はあの耐えられない風圧を避けて上半身はヘルメットをスクリーンの上に出す程度しか起こさず身構える。またもや両肩が抜けそうな減速Gに見舞われたが、左右へフロント・タイヤが逃げそうな素振りを全くみせない、まるで前輪が太くなったかのような安定さ加減にニンマリ。実は試乗前、どこからブレーキ圧が入力されるのかが掴みにくいのではないか、また、遊びがないジワッと引けてしまうようなレバータッチを警戒していたのだが、それは杞憂に過ぎないのをすぐに察知できた。ブレーキの立ち上がり加減のリニアリティが常に一定で、逆に強力かつ安心の証しに思えて扱いやすさに変わったからだ。YZR-M1のカーボン・ローターとの組み合わせは、概念的には効きはじめてからの温度上昇で、後輪がリフトしかねない急激な変化に陥りやすいはずだが、そんな兆候も全くない。フロント・フォークも急激なダンパー内圧上昇をうまく逃がしながら路面追従性を確保する、想像を絶するやんわりした足応えだ。リリースもスッと節度を感じさせない感性に馴染みやすいフィーリングに終始していた。


おまけにシフトダウンが、どのタイミングで操作しようと、一定のエンジンブレーキのままがキープされるまさにシームレスなので、後輪の接地も保たれてかなりの急減速でもライン変更ができそうな余裕を感じる。ライバルの傍若無人ともみえるスライドを伴った突っ込みに対抗するのを、大きなテーマとして開発されたと聞くと、なるほど納得の減速パフォーマンスだ。減速だけではなく、そこに自由度まで与える様々なファクターをまとめた総合力の高さは、MotoGPライダーに遥か及ばないアベレージでも自信のほどと共に切々と伝わってくる。
この急減速に不安がないとわかると、ライダーは大胆になれる。試乗前の心臓が破裂しそうだった緊張は、僅か2ラップほどで急激に薄れ、あろうことかコーナーの最初のターンで、スロットルを開けてグイグイと後輪を路面へ押し付ける走りを試しはじめていた。
リーンはロールセンターが低いコンパクトな動きだが、不思議なほど過度に鋭くはない。軽くて素早い動きだが、ある一定のリズムへ自然に同調させられる穏やかさだ。その前輪から伝わってくるグリップ感は感動モノ。MotoGPマシンにはYZF-R1Mのようにシチュエーションに対応するアクティブ・サスは装着されていないが、常にフルブレーキングからリーンへ移行していく決まった範疇のモーションであることも手伝って、ブレーキ荷重が減ってコーナリング荷重へと移行する間の前輪が路面へ押し付けられている感覚に変化がない。それでいて、意識せずとも後輪が接地感を保ったまま旋回というか、グーンと曲がりはじめてしまうので、慣れないと最初に曲がり過ぎるタイミングの合わないターンに陥りやすい。せめて低速コーナーなら可能なはずとばかり、ヘアピンでこれは突っ込みすぎ……というくらい高めの進入速度を試すと、ようやくそこそこタイミングの合ったターンになるといった具合だ。もちろんその際も、前後輪が路面へ押し付けられた感触が持続されるから、スロットルを開けるタイミングの自由度も高い。
少しは余裕を感じる大きめのコーナーで、スロットルを早めに大きく開けるチャレンジをちょっとだけ開始する。エンジン音が逞しく籠り気味に変わりながら、タイヤのグリップが路面と回転差が出るゥワゥワゥワ~と波状なサウンドとなって、実に小気味よいトラクション感覚に包まれる。もちろんMotoGPライダーのように、膝を畳んだまま路面を擦るなどという深いバンク角は、さすがにリスキーでクリッピング・ポイントでクルリと曲がる旋回など再現しようもないが、後輪とスイングアームが一体となって車体を押しまくりながら旋回加速をみせてくれる醍醐味だけでも、まさに天にも昇る心地にさせてくれる。2速のコーナーでも3速や4速のややスピードの高いコーナーでも、不思議なほどに開けてから曲がるまでのマナーに変わりがない。
それにスロットルを開けた瞬間の、ちょっとだけラグがあってやんわり後輪が路面を捉え、そこからグーンとグリップする過渡が素晴らしい。そう、どんな操作に対しても決して唐突さをみせないこのやんわりとした過渡特性だからこそ、短時間にボクを大胆な気持ちにさせてくれたのは間違いない。信じがたいだろうが、それは大型のツアラーやビッグ・スクーターにも似た、前後のサスが常にストロークを繰り返す動きを伴っている。当然、絶対的なストローク量は大きくないが、この動きこそが常に限界付近でタイヤがスライド気味ながら、方向転換や旋回力を失わない状態にキープしつつ、混戦で急激なライン変更があろうとリカバリーの効くライディングを可能にしているのだ。
と思う間もなく、ピット前を通過する際にPのサインボードが目に入る。約束の5ラップ目?エッ、もうちょっと走らせてはくれないだろうか……見落としちゃいましたとか、それはさすがに通用しないだろうナァ、等々半端なく名残惜しい気持ちに見舞われたが、慣れてくるほどにリスクが高まるのは百も承知。数ヶ所でスロットル全開の失神寸前なパフォーマンスを楽しんでピットロードへと向かった。
ライダーに安心と自信を与える。M1は「ハンドリングのヤマハ」を象徴していた
この僅か5ラップでも、MotoGPマシンに12年ぶりに乗ったボクに、全開やフルブレーキを試す気にさせる馴染みやすさこそが、最新のテクノロジーを駆使した頂点の象徴であることを、これほど思い知らされるとは正直想像もしていなかった。もっと正直にいうと、MotoGPマシンの暴れ馬を振り回すようなライディング・パフォーマンスは、そこまでのリスクと闘うことに燃える年齢などとっくに過ぎているので、YZF-R1Mのベースとなった特性だけ検証するのが目的、そう言い聞かせながらセパンまで足を運んでいた。それが、まさか、まさかの連続に終始して、短時間に楽しいとまで思えてしまったのだ。
これが電子デバイスのおかげであるのはいうまでもない。今回のテストでも、ピットにはメカニックと同じ人数ほどのラップトップと睨めっこをしているエンジニアが陣を張っていた。電子デバイスが、いまやライダーのミスをリカバーするサポート的な役割ではなく、最新YZF-R1Mでも装備されている車体のあらゆる動きの方向と速度を検知して、ライダーが扱いやすい特性に変化し続ける、完全なパッケージ化まで進化した、新しい時代の幕開けを目の当たりにすることができた。


YZR-M1は、各コーナーで異なるプログラムを反映させているのだという。ボクの試乗ではその特性変化に慣れるための時間をカットする意味もあってOFFになってはいたが、既にそこまで電子デバイスのパッケージ化が進んでいるのだ。
しかし、ここで忘れてならないことがある。このライダーに馴染みやすい過渡特性、つまりパワーや荷重で特性が変わっていくその変化率に、唐突さを感じさせない穏やさこそが、ライダーに安心と自信を与え、ライディングを楽しませるための最も重要なファクターだということ。それはどんなに多くの情報を収集しても、変化や起きたことへの対応では繊細な人間が感じる不安解消には間に合わない。如何なる変化や何が起きようとも、その都度人間が安心できる変化率をキープする必要がある。その先読みともいうべき範囲までカバーできるノウハウが、電子デバイスのパッケージ化には欠かせないだろう。
そこで思い出させるのが、まだ未舗装路が多かった時代から、ライダーが安心できるハンドリングにこだわり続けてきたヤマハの姿勢だ。ライバルが鋭さや軽快性で評価されようが、頑としてこのポリシーを貫き通してきたその歴史には例えようのない重みがある。
しかも時代が移り、開発や検証をする世代交代があると、精神は語り継がれても実態は変わりやすい。ところが驚くべきことに、ヤマハでは知るかぎりその実態も変わらず受け継がれてきている。だからこそ、人々はいつの間にか「ハンドリングのヤマハ」をイメージするようになったのだ。YZR-M1の衝撃的といえる乗りやすさは、この積み重ねなくしてあり得ない……そう確信できる、まさに「ハンドリングのヤマハ」を象徴する試乗体験となった。安心できなければ楽しくない、この先人たちから変わらない、常に人に優しい馴染みやすい感性こそがヤマハらしさなのだ。