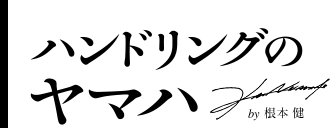Vol.9 スーパースポーツの変遷。 YZF1000RからYZF-R1へ。
歴代のスポーツバイク開発でヤマハがこだわり続けるライダーの感性に馴染みやすいハンドリング。1996年のフラッグシップYZF1000Rはその象徴的な存在である。ライバルをCBR900RRとしながらも、開発の狙いをライダーが安心してワインディングを楽しめるハンドリングとしたからだ。しかし、刺激の少ない乗り味から、デビュー当事は過小評価を受けたといわざるをいない。結果としては長寿モデルとなり、その素性の良さはハイスピードツアラーとして正当に評価され、世界中で愛されることとなった。
そして1998年、それまでの努力と技術の蓄積が世界中を揺るがす衝撃のニューモデル、YZF-R1のデビューという形となって花開いた。軽量、ハイパワー、コンパクトというヤマハらしさに溢れ、スポーツライダーたちが実際に楽しむシチェーションで最高のパフォーマンスを発揮し、心の底からコーナリングを楽しめる上質なスポーツバイクをつくりあげたのだ。
(以下、本文は1998年のライダースクラブ誌の記事に加筆修正した)
根本健
1948年、東京生まれ。慶應義塾大学文学部中退。
16歳でバイクに乗り始め、’73年750cc全日本チャンピオン、’75年から’78年まで世界グランプリに挑戦。帰国後、ライダースクラブ誌の編集長を17年にわたり務め、多岐にわたる趣味誌をプロデュースする。
現在もライフワークとしてAHRMAデイトナレースに参戦を続けている。
ヤマハのハンドリングコンセプトそのままを開発 YZF1000Rサンダーエース
'50年代後半にスポーツバイクの開発を初めて以来、一貫してライダーの感性に馴染みやすいハンドリングの追求にこだわり続けてきたヤマハ。その常に変わらない姿勢に、いつのまにかライダーの間に「ハンドリングのヤマハ」というイメージが定着してきたわけだ。その間、ライバル達のヤマハ流とは異なるハンドリングが注目を浴びた時期もあった。しかし、そこでもヤマハ流ハンドリングのコンセプトが揺るがなかったのは、開発スタッフがいつもユーザー側に立った考え方で方向を定めてきたからだ。
それをよく象徴しているのが1996年のフラッグシップYZF1000Rだろう。リッタースーパースポーツは各メーカーがコンセプトの違いを明確に打ち出した時代である。ホンダはCBR900RRで、超軽量な車体でクイックなリーンが可能という、ビッグバイクでは考えられなかったコンセプトで人々を驚かせたのだ。「YZF1000Rを開発する段階で、そのハンドリングでユーザーに衝撃を与えたCBR900RRがよく売れていた。実際に良いバイクですネ。あの操安(操縦安定性)の軽さには我々もショックをうけましたから」。当時の実車のテストチームを担当した第2プロジェクト開発室・実験担当・技員の猪崎次郎氏が、ライバルがどうあれヤマハ流コンセプトにまとめていく過程を詳しく説明してくれた。

YZF1000R テストコース走行風景 (1996年)
マーケットでリードしているバイクに対し、ヤマハも同じ路線でいくのかどうなのか、ずいぶんと論議を重ねたという。実験のチームにもCBR900RRにすっかり魅了されたライダーもいたのだ。しかし、実験チームの感性ではスパルタン過ぎるというのが結論だった。軽快さは軽量なだけでは得られない。「マーケットも認めているし、スーパースポーツの面白さをここまで表面に押し出したホンダの割りきりのよさには敬服しました。しかし、我々がいつも論議を重ねるユーザーが実際にツーリングなどで使うとき、何が大切かを決める線引きのようなものがあって、そこに照らし合せるとヤマハとしてはこのスパルタンさはどうしても許容できない」 「ただCBR900RRの軽さ、実際の車重はもちろん走っても軽いという、これはヤマハとしても強調しようということになりました」。
「先行開発で750の車体に1000ccのエンジンを積んでテストしていたのですが、エンジンそのものの重量では750と1000ではそう大きく違わないのに、走った感じだとなぜこんなに重いのかというほど1000のエンジンを積むと変わってしまう。パラ4(並列4気筒)のクランクは重いんですよネ。軽快さは車輌重量だけじゃない。ましてやハンドリングの質となると重量以外のファクターの方が大きく支配する」。


猪崎次郎氏
(インタビュー当時:第2プロジェクト開発室・実験担当・技員)

YZF1000R THUNDER ACE (1996年発売)
徹底的な軽量化により、従来のヤマハ1000ccスーパースポーツの中では軽快な運動性を実現した。セカンダリーロードでの早さ、そして楽しさが追求されたハンドリングは、レーシングマシン的なクイックな特性ではなく、ライダーが緊張感を強いられないというヤマハならではの設定。エンジンはFZR1000をベースに軽量鍛造ピストンを採用するなど各部を刷新。最高出力145ps/10,000rpm、最大トルク11kgfm/8,500rpmを発揮する。高い剛性と軽量化を果たした一体成形式Fブレーキキャリパーは、扱い易さ及び対フェード性に優れる
それはエンジンのパワーやトルクの特性でも、ライダーの感じ方に大きな影響を及ぼすのだ。もちろん車体の剛性やホイールベース、アライメントに重心位置、それにタイヤサイズなど細かな設定にも重く感じるか軽く感じるかの違いがでる。たとえば車体剛性でいえば、剛性が強すぎると操作感で重い感じになるしサスペンションもハードに過ぎると同じように重く感じるのである。要は強すぎても弱すぎてもダメというバランスが大事なのだが、ここをヤマハは伝統的にライダーである人間の感性に馴染みやすいものとしてきたわけだ。
「実験チームのライダーは、トレールフィーリングとか接地感とか、誰もが感覚的なところでタイヤと路面の関係を言い表わします。その評価でもキックバックに過敏すぎるということになった。プロがサーキットを攻めているときならば情報量が多いということもできる。しかし一般のライダーにはそういう伝わり方にはならないと思うんです」。 この発想がいかにもヤマハらしいところだ。「ヨーロッパはアウトバーンだけでなく、我が国からすれば羨ましいほど楽しめるワインディングが多い。我々はこれを高速道路に対してセカンダリーロードと呼んできた。FZR1000からはこのセカンダリーロードを重視し、YZF1000Rではさらにここにこだわった。CBRとの差別化も、結局どこを走って楽しいと思えるか、そこを明確にする必要があるというわけです」。
「ビッグバイクとしてはスピードの低い、カーブもきつい場面を大事にしようと……具体的にはワインディングの2~3速、車速にして100km/h近辺です」。ここで思う存分ライディングを楽しめるバイクにしたい。ハンドリングの質を、コーナリングを楽しめる軽快なものにしつつ、だからといって唐突な動きとならないよう刺激の少ない馴染みやすく安心感のある方向を狙ったのである。
こうしてリッターバイクとしてはもちろん、このルックスからは想像できない198kgという軽量で、余裕の145PSを誇るYZF1000Rがデビューした。しかも従来のFZRより軽やかなハンドリングを、ヤマハらしく安定感を損なわずに得るという優れたバイクに仕上がったわけだ。しかしヨーロッパのバイク雑誌の評価や反応は、それほどセンセーショナルなバイクというものではなかった。「ルックスと走りのフィーリングから、ツーリングスポーツ的な位置づけに見られてしまったようですね」。リーダー役の猪崎次郎氏はちょっと残念そうだった。しかし彼の価値観は揺らぐことはなかった。このとき既に、ユーザーにとってスペックだけではなく、そのバイクの本当の狙いは何か、それが自分のニーズに合うものかどうかをじっくり吟味できる時代になると確信していたのだ。(後編へ続く)